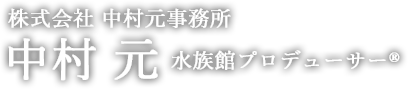近代水族館展示の潮流
近頃、水族館をトレンドという言葉で表すことに少々抵抗感を持っている。というのも、水族館文化を楽しむ利用者たちがけっして評価しない展示が、作る側の理論によって生まれ、マスメディアによってまるでトレンドのごとく煽られているからだ。
まず申し上げておく、映像によるバーチャルリアリティとの融合などと称して、プロジェクションマッピングや色とりどりの光線を水族館の展示に導入しているのは、水族館のトレンドではない。そもそも展示生物や水中景観を、見づらくしていることが水族館の展示であるわけもない。
それらはいわばVR映像館であり、映像や光にはない本物の魅力をペンギンやイルカなど「水族館的なもの」で補っているのにすぎない。あるいは、VR館や映像館の名称では人々の心に響かないのを、水族館的な名称で補っているものと捉えるべきなのだ。
巨大水族館時代
さて、水族館の潮流の本筋に移ろう。水族館の展示の潮目が大きく変わったのは、巨大な水槽が生まれてきたことによる。巨大な水槽やカーブを描いた水槽はアクリル技術の進歩のおかげだとよく言われるが間違っている。技術は必要がなければ生まれない。進化の要因はもっと単純な力、水族館への投資額が巨大化したことによる。
昭和から平成へと移るバブル景気期の日本は、港湾地区の再開発計画であふれ、その中核集客施設として目を付けられたのが水族館だった。バブル景気直前には人気動物ラッコが、それまでの水族館の入館者記録に倍する集客を達成していた。そのため海辺の再開発には、集客力が高く、巨額の投資を十分に回収できる水族館が最適!という風潮になった。つまり、水族館や水槽の巨大化は、ラッコ人気とバブルのお金で生まれたのだ。
しかし巨大な水槽やアクリルは、水族館に新しい方向性を与えた。それまでの水族館は水生生物を展示する水生動物園だったが、巨大化した水槽そのもの、水中世界を見せる「水槽」という展示物が生まれたのだ。
巨大水槽による水中の非日常世界はバブル景気の日本で熱狂的に受け入れられ、水槽の巨大化と、それにともなう水族館の超巨大化が競うように行われた。しかしバブル崩壊の後、2001年名古屋港水族館の北館オープンを最後に巨大化競争は終了した。
ポスト巨大水槽からの水塊展示
巨大水族館開発時代の終了によって、次の日本の水族館開発の主流になったのは、中規模水族館の開発だ。その戦陣を切ったのが、2004年に建替えられた新江の島水族館の中規模水族館としての成功だった。この案件は筆者の水族館プロデューサーとしてのデビューでもあり、当時のインタビューには「ポスト巨大水族館時代の水族館だ」と答えていたが、実際にこの後、国内で開発あるいは建替えられる水族館の主流は中小規模となった。
規模が一気に縮小された理由は、景気の後退のせいだったが、ダーウィンの進化論は水族館の進化にも当てはまる。展示は社会環境に適応して、小規模でも魅力的な展示へと進化をしてきたのだ。
その変化の主流は主に、僭越ながら水族館プロデューサーである筆者とそのクライアント水族館との協働によって生まれてきた展示を紹介することで述べることになることを許されたい。
水槽が生物を飼育展示する器から、水中世界を再現する展示物へと役割を変えたことで、水族館の利用者層も、生物好きの子どもから、海中を体験したい大人へと劇的に変化した。
大人たちは巨大な水槽やアクリル見るのではなく、巨大な海の水中世界の体験を楽しんだ。ならば、水槽の大きさに頼らず対応する方法はある。それが筆者の定義した展示『水塊展示』だ。『水塊』とは、海や川に潜って、見たままの光景や感動を手頃な大きさの塊にして水族館の中に持ってくることだ。水中の環境を水槽に再現するのではなく、水中世界を塊にして持ってくるイメージだ。
それまでの擬岩や擬サンゴだらけになっていた水槽は、海の本質を表してはいない。海とはどこまでも青に包まれた無限に広く深いものであり、私たちはその壮大さと青い世界に魂を奪われるものだ。
海に潜るダイバーが目を奪われる、どこまでも続く青色の水中世界、心身ともに揺らす浮遊感、天上からの暖かさと明るさを感じられる太陽光の揺らめき、立体的に形を変形させ輝きながら泳ぐ魚たちの群れ、そういった感動を再現することに傾注して水槽を開発すること、それが『水塊展示』である。
展示開発の原点
水塊展示を実現するのに絶対的に必要なのは企画力でも技術力でもなく、水中世界の経験的知識であり、展示生物の生態を実際に観察した経験だ。なぜなら、水族館の本分とは「展示」であり、展示とは見せて伝えることだからだ。本物の自然・本物の生物の生き様を知っていなければ、展示の主体となる水槽を企画することなどできない。
生物学の知識はあまりない筆者が水族館展示をプロデュースできるのは、世界中の海や川の水中を体感し、そこに住む生物の生態を撮影してきた経験と知識による。大衆に見せて伝えたいことが山ほどあるのだ。それゆえ、展示とは建築家や空感デザイナーがおいそれと手を出せるものではない。美術館を作ることはできても、そこに展示する絵を描くことはできないのと同じ理屈だ。
ただし設計者にも方法はある。水族館の飼育係の中から「展示係」の意識とフィールド体験のある者を探し出し、協働して展示開発をすればいいのだ。実はこの方法は筆者も使っている。自分の体験に無いことは、誰かの体験を活かせばいいではないか。
本来は、学芸員にこそこの展示開発の職責があるはずだったのだが、日本の学芸員の多くが、理科教育だの生物研究だのといった枝葉末節の追求に明け暮れる教育を受けてきたために、最も大切な「展示」能力に欠けていることが多い。実にもったいないと感じる。
水塊展示開発の技術
さて、水塊展示の開発における技術的なことを述べよう。水塊を実現するのに重要なのは、水槽の大きさを感じさせないことと、水の存在を感じさえることだ。そこに、浮遊感や清涼感を演出すれば、かなりの水中感を持つ水塊展示が生まれる。
以下にその基本を述べるが、その前に知っておくべき最重要ファクターがある。水槽には水が満たされるわけだが、水の入った容器は屈折によって見かけの奥行が3分の2ほどに圧縮される。水そのものは光を拡散させることで塗装色を薄め立体を平坦に見せる。特に曲線的にカーブしたアクリルの水槽は、レンズ効果が重なって、水のあるのと無いのではまったく違ったように見える。このことはよく研究しておきたい。
『奥行感』 筆者は30年前に新鳥羽水族館の展示開発責任者だった時から、水で満たされた容器の奥行きの圧縮や平坦に見せる性質に対抗する方法をいくつも考えて実践したが、その後も新たな水族館を手掛ける度にその技法を進化させ新たに開発してきた。
今では小さな水槽をどこまでも広がるように見せる方法はいくらでもある。壁の色、擬岩の使い方、照明や影の使い方など。演劇の舞台を建て込むように、あるいは絵を描くように、もちろん水に満たされた水中の性質を考慮しつつ景観を構想し作り上げる。
水槽を広く見せるには、水槽の内部を水中色にして壁の存在を消すのが効果的だが、それだけには飽き足らず、水槽の角を丸め濃い紺色にすることで影による存在を消すことや、照明のグラディエーションで奥行を創るホリゾントスペースの設置、さらには青空を借景にして無限の広さを感じさせることなど、様々な方法にたどり着いた。
『水流の存在』 海に比べるとはるかに狭く浅い川では、水流の存在を見せることで水塊を創り出した。私たちは川底や岩肌の景観よりも、川の流れに水の力と清涼感を感じる。どれほど見事な擬岩や植栽が再現されていても、目に見える水流がなければ川ではない。水流が空気の粒を巻き込んで流れれば、その流れる様子は銀色に輝く空気の線となって、あるいは激しく跳ね回る気泡となって現れる。
その流れは人々の目を奪い川の力を感じさせるだけでなく、同時に展示されている魚たちの激しく活き活きとした泳ぎを見せさせる。この成功は、後に海の展示でも岩場の波を水中で砕けさせる水槽の開発に繋がった。
『浮遊感』 水槽のジンベエザメが目を引くのは、魚類最大の大きさだけではなく、水中という空感に巨体が浮いているという不思議な浮遊感によるものだ。浮遊感こそは海を潜るダイバーにとっても最大の喜びの一つである。それをジンベエザメの巨体によって視覚的に感じることができるから人気なのだ。
この浮遊感を最大限に活かしたのがクラゲの展示だ。中でもクラゲ水族館の異名をとる加茂水族館にある直径5メートルのミズクラゲの大水槽は、世界の水族館に大きなインパクトを与えた。日本国内にクラゲ展示が増えたのはもちろん、中国では超巨大クラゲの水槽が次々と建設されている。何を隠そう筆者がサンシャイン水族館と開発した最新の展示も、水槽幅では世界最大級のクラゲ水槽だ。もちろん何よりもクラゲの浮遊感を最大限感じられるようにした。
動物園の水族館化
動物園の水族館化も近年の特徴だ。言うまでもなく、旭山動物園の水のチューブを垂直移動するアザラシ、トンネルから見上げるペンギン、飛び込むホッキョクグマなどが大ヒットした。旭山動物園はこれらを「行動展示」と名付けて有名になったが、行動展示が集客に成功したのではない。これらの展示が注目を浴びた理由は、乾いたイメージの動物園に、水中世界の潤いや清涼感、そして何よりも、巨大な生物たちによる浮遊感などの「水塊」が生まれたことによる。その証拠に、水槽を使わない行動展示もたくさんあるのに、メディアに取り上げられ、観覧者が殺到したのは水槽展示だけだった。
動物園の水族館化で新たに注目を浴びたのは、同じく北海道の円山動物園だ。ホッキョクグマとアザラシの巨大なプールと水中トンネルは青い水塊が気持ちよく、大人の女性ファンが朝から張り付いている。両生類は虫類館ではワニの仲間やカメ・カエルなどが水中世界や水辺環境で暮らし、水族館の両生爬虫類コーナー以上に観覧者の多い展示棟になっている。さらに新しくできたゾウ舎の深いプールは水中を観察できて人気だ。
実はこのような水族館化現象は動物園だけに留まらず、科学系博物館にも広がっている。これらの展示にも水塊展示を導入することができたなら、長らく古いハイカルチャーのまま停滞していた日本の文化施設も、欧米の文化施設がマスカルチャー化したのと同じように、大衆文化として発展するだろう。水族館展示の発展は、日本の他の文化施設の展示文化の発展の先駆けとなるはずだ。